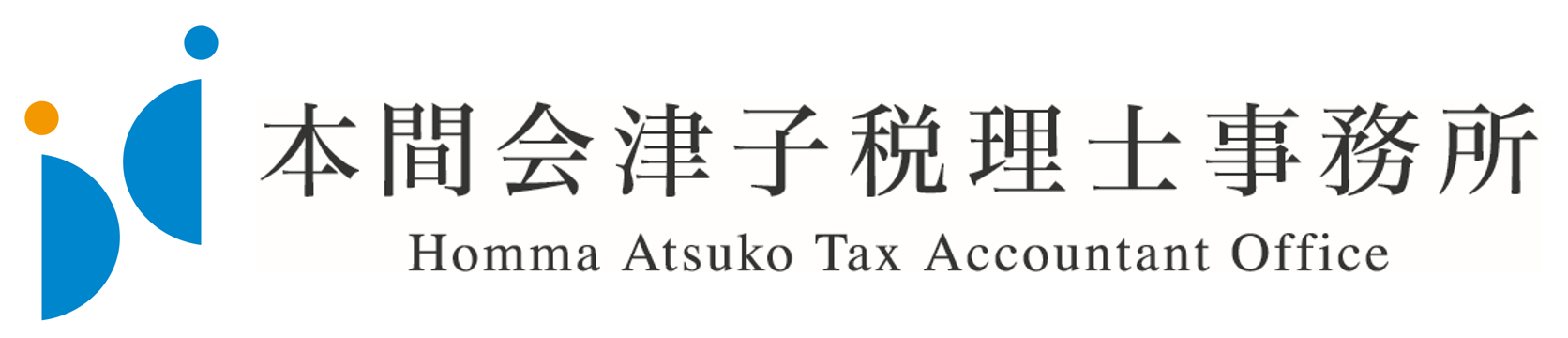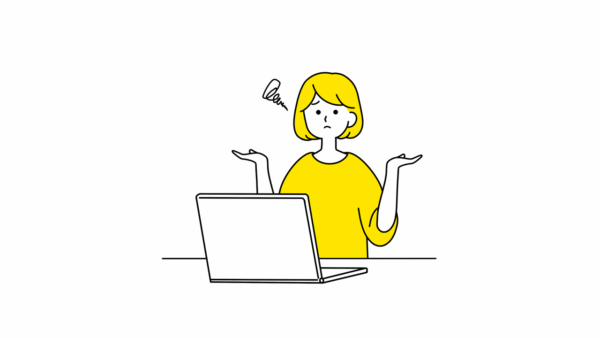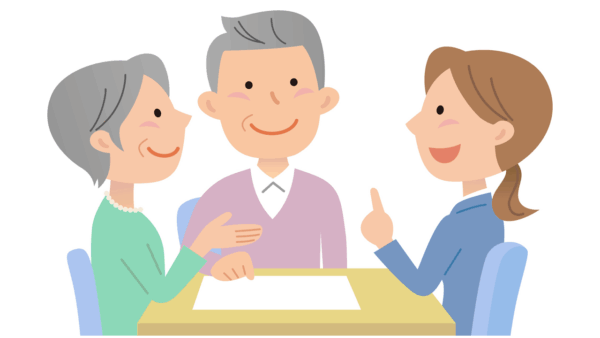- 亡くなってから半年以上経ったころ、税務署から相続税申告のお尋ねが届いた
- 相続税がかかりそうとは知っていながら、めんどくさくて後回しにしていた
- 遺産を整理していて、「ひょっとして相続税がかかるかも」と不安になった
このような理由で、相続税の申告期限ギリギリになってから税理士に相談するケースがあります。
相続税の申告期限は、お亡くなりになってから10ヶ月以内。
結構あっという間であり、気づけば申告期限3ヶ月前を切っていた、ということも少なくありません。
ご依頼が申告期限ギリギリになった場合のリスクをお伝えします。

「相続税がかかるかな?」と思ったら、早めのご相談をおすすめします。
相続税申告は、「遺産の金額を集計して終わり」という単純な作業ではない
もしかすると相続税申告は、「亡くなった時点の遺産の金額を集計して、申告書ソフトに入れればあっという間に終わるんじゃない?」と思われるかもしれません。
しかし、それはまったくの誤解です。
相続税申告にはかなりの作業を要し、税理士だけでなくお客さまにお願いするものもあります。
申告までに時間がないと、財産を把握しきれないリスクがあります。
依頼を受けてから相続財産の評価にいたるまで、どのようなスケジュールになるかをざっくり紹介します。
お客さま側で資料集めが必要
まず相続税申告の場合、税理士と初対面であることが多く、「家族構成は?」「どんな財産を持っているの?」「財産はどのように使っている?」「家族間でお金のやり取りはなかった?」「過去の申告の状況は?」「遺産をどうやって分けたいの?」など、いろいろお聞きする必要があります。
そして相続税申告は、「お客さま側で資料を集めてもらう」ところからはじまります。
この資料が集まらないことには、申告書の作成に着手することができません。
「資料集め」はかなり時間を要します。
1~2ヶ月かかることが多く、この時点でスケジュールがすでにギチギチです。


最近では、財産がネット上にある「デジタル遺産」も多いです。
亡くなった人が家族にその存在をきちんと話していればいいのですが、そうとも限りません。
デジタル遺産は、紙の証書よりも探すのがより困難になります。


財産の評価
お客さまから資料をもらったら、いよいよ税理士サイドで財産の評価をします。
財産の評価は決して簡単ではなく、時には判例などを調べます。
財産のなかでも特に評価が難しいのが「不動産」。
不動産は、どのように使われているかによって評価額が異なります。
また「土地の形がいびつ」「ふつうの土地に比べ、利用するのに障害がある(傾斜がある、高圧線が通っている、忌み地である、など)」などの要素があるかどうかを調べ、減額できるポイントがないかを調べます。
場合によっては、土地の現地調査や役所に話を聞きに行くなども必要になります。
お金の流れの把握
相続税申告では通常亡くなった人の通帳を遡れるだけ遡って見せてもらいます。
場合によっては、相続人(ご家族)の通帳も見せてもらいます。
なぜそんなことをするのかというと、
- 家族間でのお金のやり取りはあるか(贈与や貸し借りを行っているか、名義預金はあるか)
- 使途不明の大きな引き出しはないか(把握していない別口座に預けていないか、大きな買い物をしたが相続財産から漏れているものはないか、もしかすると現金で隠している?)
- 不明の入金はないか(貸し借り?何か売った?)
- 亡くなる直前に多額の引き出しを行っているか(相続財産に加算すべきか)
- 保険料を払っているか(把握していない保険契約があるかも)
- その他、相続財産から漏れていそうなものがないか
このように通帳のお金の動きを見ることで、いろいろなことがわかるからです。
この作業は、税務署が税務調査に来る際必ず行うものです。
それを相続税申告の時点で行い、なるべく財産の計上漏れをなくそうというのが狙いです。
お金の流れについては、お客さまへ質問する事項が多いです。
それを思い出したり、調べてもらったりするにも時間が必要です。
遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合
遺言書がない場合、相続人全員で遺産をどう分けるかを決めなければなりません(遺産分割協議)。
相続税は、遺産分割協議書をもとに、各相続人が相続した遺産の額に応じて計算します。
もし申告期限までに遺産分割協議が整わない場合であっても、申告期限を延長することはできず、とりあえず遺産を法定相続分で分けたものとして申告し、納税を行います。
ここで注意したいのは、遺産分割協議が整わない場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」という相続税を大きく減額させる特例が使えないため、いったん多額の相続税を払わざるを得ないことです。
ただし、特例の適用については救済措置があります。
相続税の申告書と同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を税務署に提出すれば、遺産分割が確定して申告のやり直し(更正の請求)をする際に特例の適用を受けることができ、多く払いすぎた税金を返してもらえます。
とはいえ、仮であっても多額の相続税をいったん払うのは、家計にとってかなり負担になるでしょう。
税理士に申告を依頼する場合、たいてい税理士サイドで作成した財産目録と遺産分割案(相続税額やご家族のご意向などをもとに数パターン用意)をもとに遺産分割を行うことが多いです。
そのため、税理士への申告依頼が遅くなると、家族で遺産の分け方について話をする時間が限られ、最悪の場合は未分割のままいったん申告せざるを得ないリスクがあります。
まとめ:相続税の申告依頼が申告期限ギリギリになったときのリスク
- 資料集めが間に合わないかもしれない
- 把握しきれない財産があるかもしれない
- 調べるのに時間が限られる
- 遺産分割協議が間に合わず、いったん多額の納税が生じる
相続税申告は作業量が多く、しかも大事な部分をお客さまに決めていただかなければなりません。
作業時間も考える時間も必要です。
「ウチはそんなに財産はないからすぐに終わるよ」と思っていても、フタを開けたら実はたくさんあった、というケースもあります。
「もしかしたら相続税がかかるかも」と不安に思ったら、早めに税理士に相談されることをおすすめします。