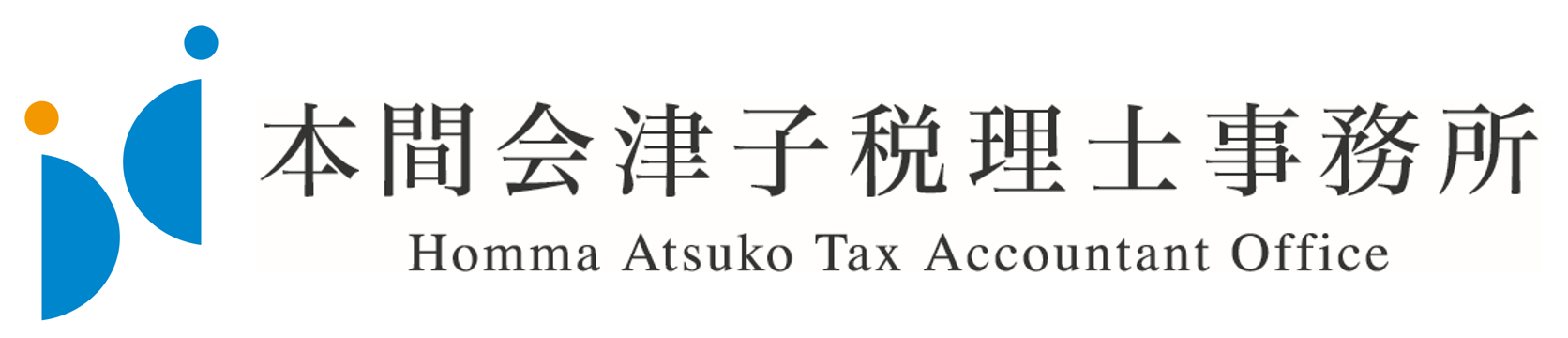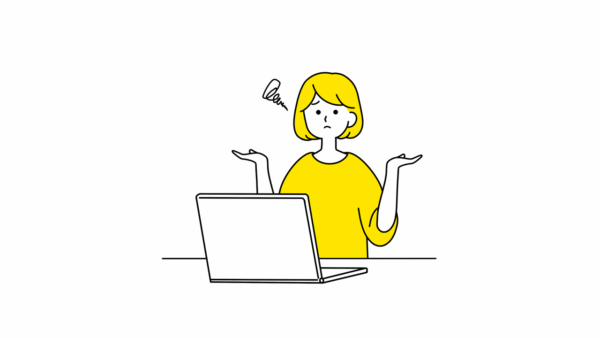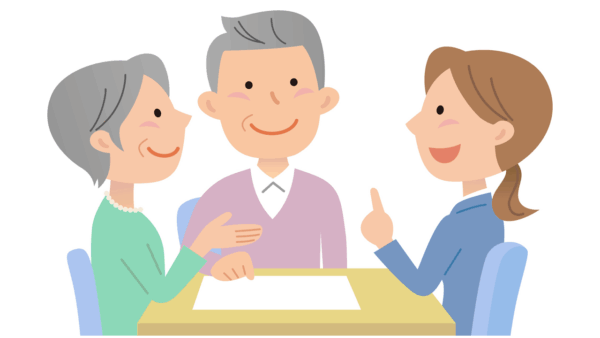相続税の申告を税理士に依頼した場合の作業の流れは、
- ご契約
- 資料集め
- 財産評価
- 不明点のご質問
- 遺産分割(遺言書がない場合)
- 申告書の作成
- 相続税の納税
となります。
しかし税理士に依頼したらお客さまは何もしなくていい、というわけにはいかず、どうしてもお客さまにお願いせざるを得ない作業があります。
上記の作業の中でお客さま側にお願いするのは、「2.資料集め」「4.不明点のご質問への回答」「5.遺産分割」「7.相続税の納税」の4つです。

お手数おかけしますが、ご協力お願いいたします。
このうち納税以外の3つについてお話いたします。
資料集め
相続税申告は資料集めが重要であり、どうしてもお客さまにお願いせざるを得ません。
集めていただく資料は、
・戸籍謄本等
・過去から現在までの通帳
・不動産に関するもの
・有価証券に関するもの
・保険契約に関するもの
・契約書関係
・残高証明書
・葬儀費用
・亡くなったあとご家族が支払った医療費や税金の領収書など
・過去の申告書
など、亡くなった人に関するありとあらゆる書類が必要になります。
資料集めはあちこちから取り寄せたり、実家を探したりするため、だいたい1ヶ月~2ヶ月かかります。
お客さまが亡くなった人の財産状況をすべて把握していればいいのですが、そうでなければ郵便物や通帳、メールからどんな資料がありそうか推測しなければなりません。
税理士の申告書作成作業は、お客さまから資料をお預かりしてからスタートします。
不明点のご質問
お客さまから資料をお預かりした後、税理士はだいたい1ヶ月~2ヶ月かけて財産を評価します。
その際、どうしてもお客さまへの質問事項が発生するため、お時間をいただきお聞きします。
亡くなった人や財産にまつわる詳細な話(例えば過去のお金の使い道など)をお聞きするため、メールよりもご訪問することが多いです。
場合によっては追加で資料をお願いすることもあります。
遺産分割
不明点が解消すれば、税理士は亡くなった人の財産の評価を終わらせ、お客さまにご報告します。
お客さまはそれを元に遺産を分けます(遺言書がある場合を除く)。
遺産はお客さまが自由に分けて構いませんが、「そう言われてもどう分けたらいいかわからない…」となるかもしれません。
そこで税理士は参考になるよう、お客さまのご意向や税金の負担を踏まえ分割案を数パターンお出しします。
分けるのに、もちろん数日かかってもかまいません。
遺産の分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成し、申告書の提出・納税となり、すべての作業が終了します。
***
相続税申告のすべての作業が終了するのは、ボリュームにもよりますが、ご契約後早くても3ヶ月、たいてい半年近くかかることが多いです。
税理士と会って打合せをするのは、私の場合「初回面談」「中途のご質問」「財産評価終了後のご説明」の3回が多いです。



税理士さんに依頼しても、結構時間がかかるのね。



お客さんもいろいろやることがあるんだね。



スケジュール感やお願いする資料は、あらかじめご説明いたします。
相続税申告ではお客さまのご協力が欠かせない、ということを知っていただけるとうれしいです。